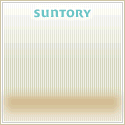食物繊維
食物繊維は、なにかと問題のあるダイオキシンなどの環境ホルモン(体内でホルモンのように働き、身体の機能を乱すといわれる物質)から私たちを守ってくれます。 ダイオキシンは、多くの場合、食物を通じて私たちの体内に入ってきますが、その60%は魚介類からです。化学製品などの焼却によって、大気中に排出されたダイオキシンは、川に溶け込んで海水中に蓄積され、魚の体内に取り込まれるからです。 食物繊維は、私たちの小腸内でダイオキシンを吸着し、対外に排泄してくれます。ですから、食物繊維をたくさん摂ることで環境ホルモンの害を少なくすることが出来ます。
食物繊維は「人間の消化酵素で消化されない食品中の難消化成分」です。 食物繊維を一日17〜20gは摂りたいものです。かつては、栄養の面からは価値のないものとされていました。 現在では大腸癌をはじめとした、生活習慣病の予防に役に立つ栄養素として、蛋白質・脂質・糖質・ビタミン・ミネラルとならんで 「第6の栄養素」として注目されています。 食物繊維自体は消化されないので、栄養にもエネルギーにもなりませんが、体の中を通過するときに体に良い影響を与えます。 たとえば、胃の中では水分を吸収して約10倍に膨らみ、便のカサを増やし排便を促します。 体内では食物繊維を摂取することによって、腸内でビフィズス菌などの良い菌を増やし大腸菌などの悪い菌を減らして、腸内の環境を良くします。加えて、発ガン物質を排泄したりすることによって、大腸癌の予防に役だっています。
さらに、糖尿病・高脂血症・高血圧・肥満などの生活習慣病の予防にも効果を発揮しているのです。 「肥満」「高血圧」「糖尿病」…生活習慣病が気になる方へ 食物繊維の種類はとても多く食品によって含まれる種類も異なります。 大きく分けると水に溶けるもの(水溶性食物繊維)と水に溶けないもの(不溶性食物繊維)とがありますが、それらは性質も働きもそれぞれ違います。 たとえば、りんごや苺など果物に含まれる「ペクチン」やこんにゃくにある「マンナン」海藻のヌルヌルした中に「アルギン酸」などが水溶性食物繊維です。 穀物や野菜に多い「セルロース」や「ヘミセルロース」などは水に溶けない不溶性食物繊維です。 働きもそれぞれ違いがあり、水溶性の食物繊維は大腸の粘膜の保護をします。 不溶性食物繊維は便量を増し便の硬さを適度にしながら移動し、腸内にビフィズス菌などの良い菌を増やす働きがあります。便秘の予防と同時にどちらも大腸癌予防には効果的に働きます。 食物繊維は昔から穀類や芋・野菜・海藻などを多く摂る日本人の食卓には欠かせないものでした。しかし、最近では食生活の内容の変化などにより摂取量が1/20にまで減ってきています。
とは言っても、摂り過ぎは下痢のもとです。食物繊維は、過剰摂取すると下痢の症状を引き起こしてしまい、必要なミネラル分まで排出させてしまうので、注意が必要です。
大腸癌との関係を調べた結果、たとえば、「リグニン」「キチン・キトサン」などの食物繊維は胆汁酸を吸着するので、腸内の有害細菌が胆汁酸からメチルコラントレンという大腸癌をひきおこす有害物質を作るのを押さえることがわかりました。 また、食物繊維は便のカサを増すので排便を促進したり、有害物質を希釈し発癌を抑えることも考えられています。
果物に多いペクチンや、海藻に含まれるアルギン酸など水溶性の食物繊維には、血清コレステロール低下作用があります。 また、食物繊維は全般的に低エネルギーであると同時に、大腸で腸内細菌により発酵され短鎖脂肪酸が生成されます。 これが吸収され コレステロールの合成を抑制することも考えられています。
また、食物繊維が多いとよく噛んで食べなければならなくなるので、ゆっくりと消化吸収がおこなわれることになります。 それに、食物繊維には栄養素が腸管において吸収される時間を、遅らせる作用もあります。 それらのことによって、食後の血糖値の上昇が緩やかにおこなわれることになります。 これは、インスリンを無理なく作用させることになり、糖尿病が引き金になっておこる合併症の予防につながります。 それと、多くは期待することはできませんが、食物繊維が便となって体外に排泄されるときに、一緒に食品中の糖分を僅かながら、排泄するともいわれています。 糖尿病の食事療法では、バランスの摂れた食事が重要とされます。そのなかでの食物繊維の働きは重要です。

|
この改行は必要→