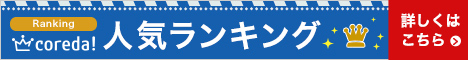
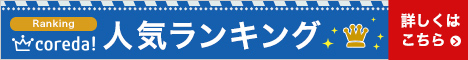
 |
桐たんすの相徳さんは、桐たんす一筋に創業
明治13年の老舗のメーカーさんです。
桐たんす 桐が大切なものの保管収納には非常に優れた材で、内部に湿気を通しにくく内部の湿度を一定に保とうとする力があります。昔は、桐の良さを多くの方がご存知でしたが、時代とともに だんだんそうした知識も受け継がれなくなってしまっているようです。大切なものの保管 きもの・呉服・帯・書画骨董・刀・矢などはもちろんのこと、磁気媒体の保管にも適しています。また、肌さわりも柔らかく温度も気持がよいことから肌に触れるところでの使用も多くなっています。こうした桐の良さを幅広く知っていただきたい。また、伝統工芸の技を知っていただきたいとおっしゃっています。 |
|
|
桐箪笥、桐タンス、桐たんすと表記の方法もいろいろあるようです。現在は一般的に<桐たんす>と表すことが主流のようです。
桐タンス、外来品でもないのにタンスとカタカナ表記されるのは不思議です。桐箪笥は若い人には読みずらい。
桐たんすとやったほうが、現在ではシックリくるということなんでしょう。
さて、
東京桐箪笥は最上とされる会津桐や南部桐を使って、一棹一棹丁寧に仕上げられています。
江戸職人の技と気質を受け継ぐ東京桐箪笥。
美しい柾目やしっとりとした色調は室内調度品として独自の気品と優雅さを持っています。
かつては、女児が生まれると桐の木を植え、やがて嫁入り道具として成長した木で桐箪笥を作る風習がありました。
湿度の高い日本では軽くて柔らかく通気性に富んだ桐は衣類や大切な品々を保管するのに適した良材であることを、昔の人々は経験から知っていたのです。
さらに桐は耐火性に優れており火災のときも水がかかるとその吸収が早く、いわゆる目がつまって内側に炎が入るのを防ぎました。
日本の代表的な収納家具といえば桐箪笥。
その発生は意外に新しく、江戸時代のはじめ(1600年代後半)に大坂で作られたのが最初であるといわれています。
一般に普及したのは18世紀に入ってからで、当時は神田や浅草で製作され、
金具職人も近くに住んでいたようです。
明治時代には政府の殖産振興策によって各地で次々と博覧会が開催され、
明治23年(1890年)の第三回内国勧業博覧会には初めて洋服箪笥が登場し注目を浴びました。
東京の伝統工芸 25-26 http://dentou.aitoku.co.jp/dentou7a.htm より
|
相徳の特長 より
桐たんす 相徳の主張 (http://www.aitoku.co.jp/ait0002.htm)
相徳は
*東京に位置し
*桐たんす以外を取り扱わず
*桐の原木からのルートを確立している
*東京都家具工業組合、東京都桐箪笥工業協同組合に加盟する
*販路をデパートに依存していない
*複数の職人の製作したたんすを展示・販売している唯一の企業です。
(上記の条件の半分を満たす企業さえ全国的に考えても非常に少ないものと思われます。
いわんや東京においては、東京という条件でひとつをクリアーするにもかかわらずまず見当たりません)
ですから
相徳は桐たんすの専門商として業界でも広く認知され、原木から桐たんすの製品・流通まで
広く発言することができます。
相徳はデパートなど他の企業に遠慮することなく、桐たんす業界の発展のために
同時に一般の方に対して、桐たんすの正しい知識を普及することに努める責務があると考えています。
現在、桐のたんすとして販売されているものには
通信販売で販売されているきわめて低価格のものから一方で極めて高額のものまであります。
材においても会津桐から他の地方の桐、また外国の桐さらには桐と本来呼ぶべきでない木まで
桐と称して販売されているものもあります。こうした現状は本来の桐たんすの普及発展を考えるものからして
決して正しい姿ではありません。
相徳は本来の桐たんすの発展普及を願っています。こうした現状を憂い一般の人たちに少しでも正しい知識を持って適正な価格で 適正な品質の桐たんすをお買い求めいただきたいと願っています。
|
東京手作りフォーラム 東京手作りネットでもご健闘中の 桐たんす 相徳さんの作品をお楽しみください。
画像にブレが有るものは管理人がサイズ変更をしたためです。画像をクリックしていただくと素敵な写真に出会えます。 |
|
|
|
|
|
| |
|
| |
|
|
|
|
 |
会津桐 まな板 |
|
 |
桐すのこ |
|
|
| |
|
|
|
|
 |
短冊掛A 会津桐
たんすの端材の活用です
|
|
 |
短冊掛B 会津桐
たんすの端材の活用です
皮部分もついています
|
|
|
 |
正座椅子 |
|
 |
正座椅子を納めた様子 |
|
|
|
 |
アクセサリーボックス
★盆石(お盆の上に 石・砂などを使って絵を描きます)用の 砂や羽をしまうための砂箪笥です。アクセサリーの収納用にもお勧めです。★ |
|
|
たんすは昔、棹(さお)を通して担いだそうで、たんすを数える単位は「一棹」、「二棹」となっているそうです。
☆たんすの数えかたについて
|
|
相徳さんへ寄ってみる
☆相徳 桐たんすさんへの地図 |
|
桐の用途
今日、桐の用途はかなり多岐にわたり、単にたんすや箱にとどまるものではない。
桐の特長を生かし、たんすや箱などの中身を守ることに主眼を置いての活用。
肌触りや体感温度を生かしての下駄などへの活用。
木目込み人形などへの活用。
両者を生かしての床材や壁材としての活用。
同一性や音響効果を生かしての琴などへの活用。
さらに吸湿性や保温性を生かす活用など多岐にわたる。 |
|
☆桐の特長-桐について
☆ギターへの活用例
☆桐たんすの金具
☆桐たんすの更生
|
|
|
|
|
|
|