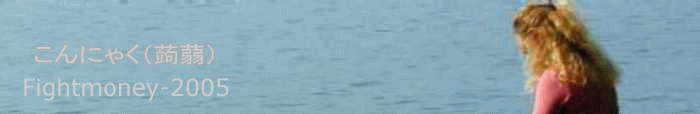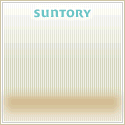こんにゃく(蒟蒻)
蒟蒻(こんにゃく)が日本に伝来したのは、縄文時代に他の作物とともに導入された、という説や仏教とともに中国から導入された。などいろいろな説があります。 少なくとも大和時代には薬用や食用として日本に伝わってきたのは確実とされる。 しかし、一般に食されるようになったのは安土桃山時代、庶民に広く渡るようになったのは江戸時代からとされている。東南アジア原産。 こんにゃくを食用としている地域はミャンマー、中国、韓国、日本で、農産物として生産され、市場に流通しているのは日本のみだそうです。日本での主産地は群馬県で国内産の約9割を占めるといわれる。 「ぜいたく庵さん」は群馬県下仁田にあるこんにゃく屋さんです。
世界で一番大きな花はこんにゃくの花だそうです。
昔の人はこんにゃくを「胃のほうき」や「おなかの砂おろし」と呼び、大掃除のあとには必ず体内の毒さらいに食べるという習慣があったそうです。 近年、問題になっているP・C・Bなど有害物質の体外への排出に、こんにゃくに含まれているグルコマンナンが有効だと研究発表もされています。 食品添加物の安全性、ダイオキシン等が心配されている現代、こんにゃくは腸壁をきれいにし、毒くだしをしてくれるのです。
便秘の救世主は、野菜などに含まれている食物繊維。このことは多くの方が知っているのではないでしょうか。 では、野菜以外で便秘の解消に役立つ食物は何でしょう? 一つ挙げられるのが、腸内環境を整えてくれるヨーグルトに含まれる、いわゆる乳酸菌やアシドフィルス菌です。 そしてもう一つは、日本人の知恵から生まれた食材、そう、こんにゃくです。 こんにゃくの主成分、コンニャクマンナン(別名:グルコマンナン)は、ローカロリーの上、腸内で水分を吸収し膨張するために、便秘の解消には最適です。 もし、あなたが便秘気味で、肌荒れ、吹き出物、イライラ、肩こり、口臭、不眠、などに悩まされていたとしたら、こんにゃくを食事に取り入れるなどして、食事内容を改善してみるといいと思います。 また、こんにゃくには、便秘解消のほかに血糖値の上昇を緩やかにさせる作用も ありそうです。
コンニャクマンナンは、こんにゃく芋に含まれるグルコースとマンノースからなる多糖の成分です。 水溶性(水に溶ける)の成分なのですが、こんにゃく芋からこんにゃくを製造する過程において、水酸化カルシウムなどのアルカリ性物質が加えられ、非水溶性(水に溶けない)に変化します。 この非水溶性が、便秘解消のポイントとなります。 非水溶性のコンニャクマンナンは、体内では消化されず、そのまま腸まで運ばれ、腸壁が刺激され、大腸のぜん動運動が活性化し、お通じがよくなるのです。 また、こうした一連の作用は、腸に便がたまることを防ぎ、また有害物質も排除するため、大腸がんを予防するためにも良い、と言われています。
まず、コンニャクマンナンは、消化管の中で食べ物を包み込んで、消化吸収させない性質を持っています。 脂肪や糖、塩分などが小腸で吸収されるのを防ぐ(完全に防ぐわけではありませんが)ため、高脂血症予防や糖尿病を予防するために良い、と言われています。 さらに、コンニャクマンナンには食後の血糖値の急激な上昇を防ぐ働きもあります。 コンニャクマンナンは、胃の中でゼリーのようなかたまりになり、ゆっくりと腸に向かうのですが、このように、食物が胃の中に長くいることで、ブドウ糖の吸収が穏やかになり、血糖値が一気に上がってしまうのを抑えるのだそうです。 血糖値が気になる方へ
普段から心得ておいたほうがよい便秘解消法を、ざっとみてみましよう。 野菜の豊富な食事をきっちりと食べる。 お水を一日最低2リットルほど飲む。 適度な運動を定期的に行う。(ソレハソウダガ・・・) 以上のことを実践すると、便秘を防止することができる、と言われています。 こんにゃくを食べることと平行して、上記の便秘解消法を実践すれば、やっかいな便秘ともさよならできるかもしれませんね。 とは言っても、摂り過ぎは下痢のもとです。 食物繊維は、過剰摂取すると下痢の症状を引き起こしてしまい、必要なミネラル分まで排出させてしまうので、注意が必要です。
日本の食事にも浸透した欧米型の食事は動物性タンパク質を多く摂っています。それは、余分なタンパク質が腸内細菌の作用で有害化してしまい、その中には発ガン性の物質も含まれているといわれています。 こんにゃくなどの食物繊維の多い食事によって、有害物質の発生を抑えるうえ、体外にスピーディに出してしまうので、有害物質の腸からの吸収を妨げ、腸内の善玉菌を増やすことにつながります。 その結果、腸ガンの発生を抑えると考えられています。結構ずくめのたいへん有り難い食材、こんにゃくです。
こんにゃく博士?になれます。カナ。
同じ頃、関西地方では、板こんにゃくを細く切って糸状にした物を糸こんにゃくと言っており、元々は明らかに違う物であったと言われています。 しかし、現在は、糸こんにゃくも白滝もこんにゃく粉を水で溶いて出来た、糊状のものを細い穴に通す製法ですので、両者を区別する方法はなく、主に関東地方では白滝、関西地方では糸こんにゃくと呼ばれています。 また、糸こんにゃくをより細くしたものを白滝と呼んでいるところもあります。
日本には昔から、こんにゃく、豆腐、納豆等、伝統的なヘルシー食品があります。 太りすぎを防ぐには、要は1日の消費カロリーよりも食べすぎないことです。といってもこれがなかなか難しいですよね。 空腹を我慢して食べる量を減らす、ダイエット食品を使う等、色々な方法がありますが、安全であまりお金をかけずに出来るダイエットとして、日々の食生活でこんにゃくなどの日本の伝統的な食品を使った料理を試してはいかがでしょうか。
織田信長が赤の長襦袢をまとい、踊り狂ったと伝えられる天下の奇祭「佐義長祭」は毎年三月中旬に日牟礼八幡宮に奉納されるます。近江八幡では、この火祭にちなんで、ベンガラで赤くしたコンニャクが作られてきました。
水府に伝わる凍こんにゃくの由来は、江戸時代に探検家木村謙次が丹波の国より凍こんにゃく作りの技術を導入したとのことです。自然の冷気の中、薄く切った こんにゃくに水をかけて凍らせ、解凍と凍結を繰り返し、乾燥したものです。
しかもこんにゃくのカルシウムは酸にとけやすく、そのために胃の中で容易にとけて小腸から吸収されます。こんにゃくが優れたアルカリ性食品なのは、このカルシウムがアルカリ性のミネラルだからなのです。
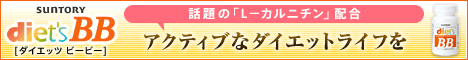
|
この改行は必要→